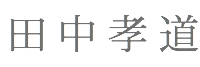「カタストロフィーへの道」
01
写真は、フィルムまたは印画紙が感光する事から始まる。私の場合、撮影はピンホールカメラを専ら使っていて、撮影後のネガを自然乾燥にゆだねているため、撮影直後のイメージは、プリントする時にほとんど保証されていない。
画面をXYマトリクスに分割して、そこでの遷移をみると、そのどこにも同じ現象は見あたらない。一カ所一カ所、一枚一枚が「ひとつ」として独立しているのである。この「ひとつ」という全体は、揺れたり軋みながら、「別なるひとつ」にむかって、たえず変わっていく。旅のエビデンスといってもいいだろう。
この旅は、「別なるひとつ」への動きを決して休めることはない。 ヘラクレイトスは、これを称して<panta rhei>と言い、私は<nothing remains>としたが、両方とも同じことを言っている。つまり、人は同じ川を二度わたることはできない、と。
02
イメージが物質に還る時、一枚のネガは崩壊の淵にある。乳剤面には、乾燥した白い物質が固着しているだけである。さらさらと崩れ落ちる物質は、かつてイメージと呼ばれていた。だが、役目をおえてそのイメージは白い粉の粒子になり、フィルム面から滑落する。イメージの終焉にたちあう時である。
マトリクスのグリッドのなかにイメージはある。当然ながらグリッドは多層空間で、ひとつのグリッドが多くのグリッドをかかえこんでいる。高次元多様体のコスモスの中に、イメージは定位しているのだが、いったんカタストロフを迎えると、そのイメージは単なる粒子の、無意味な堆積物に変わってしまう。
あのイメージの伽藍は、いったいどこにいってしまったのだろう。
03
カタストロフィーという言葉にであったのは、1970年だったと思う。ミラノのサン・フェデーレ画廊でグループ展をしたことがある。その表題が「カタストロフィー・アート・フロム・ジ・イースト」命名者は美術家の松澤宥であり、その事務局を私がつとめた。このところの写真をつかった制作をやりだして思うのは、まさにカタストロフィー [catastrophe]こそが表現の核なのではないか、と。画像が崩壊していく作法と出会い、脳髄は30年前にワープし、たくさんの美術家達を想起する。病巣の再燃か。
04
たとえば天も地も、右も左もない空間の中に自分をおいてみる。いままで良いと思っていたモノを疑ってみる。嫌いだったモノゴトを、好きになるように試みる。創造行為には、往々にして自分を裏切っていく快感が伴うものである。時には自分の足場を、取り払う試みが必要だ。
宙吊り状態や、不可測事態を友とし、それが克服できたとき、螺旋はひとまわりするのだろう。
<見切る>決断の時に、自分を前に押している。これは信じていいことだ。
05
プリントが「絵」になっていないと不安になる、これはいったいどういう感情なのだろう。プリントをみて直感的に瞬時に「絵」になっていないと、どこか気持が悪い。気分のすわりが悪い、気分の悪さを分析すると、まず初発の思いとの整合性の関係がある。つぎに構図のこと、フォルムのこと。当然付随して階調のこと、コントラストのこと、ダイナミックレンジやイメージとサイズの均衡のこと、そんな事が一瞬にして浮上してくるのである。
絵を作る時の判断も、瞬時の判断によることが多いから、それを見る時の態度も一瞬の判断を基準にするのが正しいのだ。
「見た目」や「ぱっと見」、肉眼による一瞬のスキャニングが勝負。なぜならば、眼と手と脳は、直列関係にあるからだ。
06
何度も言うように、私の写真作法はポラロイド55Tで撮影し、ネガフィルムは自然乾燥にゆだねている。つまり、無水亜硫酸ソーダ溶液での定着をしない。したがって、以下の感慨が成り立つのである。
<ネガの醸成、熟成、漂流しているネガをすくいとる、変化し続ける、終わりのない旅、戻れる確証のない、行ったきりの旅>
<ネガは私が眠っている間も、変相をかさねるネガ自身、知り得ない消失点に向って微動しているカタストロフィーは確然としやっ てくる、泰然としてネガはそのことを受容する>
その結末はどうなるか。対象、被写体の明証性は喪失し、フィルムの上にかつてイメージと呼ばれたものの残骸が残るのみである。ほとんど朧気な中に浮かんでくる若干の具象は、世界の終焉にも似て刹那の感情をたたえる。
だから何だ、という別の自分の声も同時に聞こえてくるが、再び、アンフォルメルの海に漂う日が近い。
07
私にとって暗室ワークは、(撮影によって得られた)光を培養し、しかる後に、引き伸ばし機にかけて解剖するようなもの
【暗室で 深夜さなぎは 蝶になる】
08
印画紙水洗機を満水にして、空気弁コックをひねると、勢い良く泡がのぼり立つ。この水泡が、印画紙に滲み込んでいる定着液を洗い流す。印画紙は流水に約一時間洗われていると、奥から輝きを放射する「紙の鏡」に変わっていく。制作過程では作業のすべてが同等に重要であるが、特に水洗をおろそかにはできない。
【写真とは、紙を鏡にかえる術と覚えたり】
09
プリントは光の制御。書の世界に「墨を惜しむこと金のごとし」という言葉がある。
それに倣って言うと、「光を惜しむこと金のごとし」となる。
明るい部屋にて、ひとしづくの光を畏れよ、光を惜しめ。
10
結論の先送り。逃避、遅延、このことは決して悪いことではない。それによってパラダイム、ステージ、シーンが変わる可能性があるからだ。
これを以て、「逸脱の戦略」と言えば聞こえはいいが、時に単なる怠惰となることも多いのである、この世はたえず「一寸先は闇」なのだ。
11
撮影した場所の現実感が消えて、<ひとつの風景>が出現することがある。「別の自然」「もうひとつの自然」と言った方がいいかもしれない。
たとえば、樹木を撮ったとしよう、だがある時から、その樹木は固有性をこえて、樹木総体、いわゆる樹木になっていることがある。
具体の超越、<場>の消滅と、あらたなる<場>の出現。写真はいつから<写真>になるのだろうか。幾度となくこの問いに突き当たる。
時間の溝、ずれは、ネガの中に埋めこまれている。その後、暗室でその「時間」はネガから発掘される。現実の時空から捕獲されたイメージが、過去完了継続時間を経て蘇る、イメージ考古学の時間なのだ。
【深夜の暗室でネガを掘る】
12
イメージはことばに同定できえない。写真とは、辞書にないコトバをまさぐる装置。
13
私にとって、写真が成り立つための成分分析をこころみると、人間の病理現象全体が検証の対象となる気がする。いびつで、でこぼこ、ばらばら、だから私なのか。
14
暗室に光が静かに忍びより、ここで、光の料理をする事になる。
ここで、光の料理をする。波動、粒子伝導、アラン・チューリングの夢。
暗室で起こる事柄は、物理というあらかじめ約束された世界での出来事のようだが、そこによこたわるパラメータは、未知にして不可知領域への招待状なのである。
15
物象の明証性との訣別。このことが、私にとってイメージを作る上でも、見るうえでも重要なキーワードである。さらば<名詞>、さらば<マトリックス>。
説明できないもの、曰くいい難いもの。この領域(領分、地帯、テリトリー)に眼をむける。言葉、ないし言説への置き換えが不能な世界というものがある。
メタ・フォトグラフィー。
メタモルフォーシス。
変化していく写真の写真。
写らない写真。
みえない写真。
さわれない写真。
リニアにすすむ時間の上を、もうひとつの時間がただよう。時間はいつから人間に認識されたのだろうか。表象の転相、そして進化、崩壊、たゆたう無のながれ。
恒久性を無批判にうけいれてはいけない。また、おなじように,物事の変容をいたずらに無常としてはいけない。
16
見えるものの彼方に、何があるのだろうか。存在の有無を超えて、確実に何かがそこにあるのである。そのように感得しえたものが、写像化可能かどうかは別の問題であるが・・・。
眼にみえないが感ずるものがある。<異なもの>への感覚的傾斜、没入。人間の脳の古層に存在する、ある種の非日常感覚を意識する事がある。普段は教養や常識に覆われているが、いったんめざめるとアナーキーの塊となる、近代以前のエネルギーが渦巻いているのだ。
17
写真と、その写真をつくるための、テクストやドローイングも等値である。
18
森は深い海溝のように静まり返っている。渚のようにざわざわと枝をゆらしている時もある。森は海、林は河、森はみえない。みえない森を歩く。
森から上をみあげると、地上にいるわたしが立っている。森の水面に陽光がゆらいでいる。天も地もない<場>が脳髄に遊ぶ。
19
「芸術は、時に失敗によって輝くものを得ることがある」ドイツの美学者の著作の中にあったこの言葉が新鮮だった。いわゆる描き損じのことである。「過失とは意図したものからの、意図しなかった逸脱のことである」という。無作為の作為に通ずるか。
20
画像が崩壊するほどに、画像本来の意味が浮上する。メタ・イメージ。
21
ネガを読む、アトモスフェールを読む。曲解は許されるが、十全なる凡庸は看過される。楽譜の読解もそうだろう。
22
某月某日、カメラの前に<水のレンズ>をおいて森を撮る。water lens。ガラスも水も透明度が高く、水を通してみた屈折した感じがでなかった。もうすこし歪曲したイメージが欲しい気がする。
少年の日に、川に潜って水の中から地上の風景をみたときのような感じが欲しい。幻視のような揺らめきをがないといけない。眼球をすべりおちる水滴の生理的不透明感を欲しいのである。
23
「写真」はいつから「写真」になるのだろうか。
○撮る前
○撮るとき
○撮った瞬間
○焼く時、暗室の中で
○展示したとき
○みた人の脳に作用し、DNAに胚胎したとき
写真変態論のために。
24
思念のまんなかに巣を作っている、一種の強迫観念が幾重にもあって、そこをひもといて自己の存在証明を試みても、たえず、思考対象の再定義からはじめないと前進できない。再定義を連綿とくり返すだけである。これも、ひとつの病いなのだろう。
(クリストファー・ノーランの「メメント」をみながら思う)
25
「ナショナル・ジオグラフィック」日本版発行のとき、広報ビデオの日本向け改作をしたことがあった。冒頭のナレーションに<shadow and light、that is photograph>
というくだりがあった。普通は光があってこそ影ができるので<light and shadow>とすると思うのだが、そこを裏切って<shadow and light>ときた。
ここで言うshadowとは、被写体の陰陽すべてを指しているのではないか。眼に見えているものと、見えないが予感させるもの、これらは<影>なのだ、と思ったりもした。写っていないが、感じさせるものをも含めて写真ということなのだ。
26
某月某日、夜更けに目覚める。読みさしの本のあいだにあった古い写真をみる。茶褐色で銀が浮いていて、光の反射具合でソラリゼーションのようにも見える。支持体と乳剤のあいだの微粒子たちが、ゆっくりと時間を積み上げている。銀が時間を吸い込んで蓄積する。銀は艶かしく生きているようだ。
酒井抱一の秋草の絵の中や、本阿弥光悦の短冊に黒いかたまりがある。永い時間によって、紙や絹の上の銀が黒変したのだ。このことを抱一、光悦は予測しえただろうか。
27
川の流れを眼で追う。(水)というものの一群れの移動。もともとは一滴の水がくっつきあったり溶け合ったりして、ひとつの無限の塊となって移動していく。
川は流れている(流れる川を見るわたしを、わたしは見ている、わたしのなかの川が一緒に流れていく感覚にとらわれる。眼球から入った川が私を流していく)かなり以前に、川をみていて、それだけで溺れた人がいたという話を聞いたことがある。
飯島耕一の詩でギクリとしたことがあった。「きみの みじめさは 内部に大河をもっていない ということに つきる」さらにつづけて、「言えることは きみの みじめさは 内部に大河をもっていない ということだ」詩人はそうたたみかけてきた。某月某日、千曲川のほとりにて。
28
われわれが見ている世界は、透明な層が重なってできている。という見方もある、今の私はそう考えている。<写生>という行為は、この層のかさなリを可視化することなのだ
風景を写生することと、風景を写真機で撮ることのちがいを考えてみる。写生と写真の結果は、似ているようだが生成プロセスは全くちがうし、結果はさらにちがう。
写生は眼と手の往復運動で、みた事物を手を使って紙に移すことが主眼である。紙の上にしるされた痕跡は、眼と手による意識の足跡のようなもの。だから、すべての痕跡は自覚的なことがらである。眼と手が選びとった結果なのである。
ところが、写真には覗いたファインダー域全部が写っている。眼とレンズはちがうものをみている以上に、実はレンズは単なる入力ディバイスに過ぎない。レンズには対象から何かを選ぶ力は備わってはいない。
あるものを撮ろうとすると、撮ろうとしない周辺ものまでもが写ってしまう。だから、写っているものすべてが、撮ろうとしたものではないのだ。なんと言う不自由さ。
だが、撮像素子が撮影者の脳とコミュニケーションを持つ事になると、話は別で、このところを軽々と超える日は近い。
29
ひとにぎりの粘土を、力いっぱい握りしめる。(何秒かして)てのひらを開く。粘土には、てのひらの虚空間と体表が転写されている。てのひらの密着焼き(コンタクトプリント)である。
写真の世界でいう、密着焼きというのは、ひとつの手法にはちがいないが、むしろ、それは思想であるといいたい。この直接性と肉体性が提示している世界を、仇やおろそかにしてはいけない。
おそらく縄文人など古代人の造形感覚を下支えしていたものは、このストレートな行為と、不可視な畏敬対象への一途な感情であったはずである。縄文人のこころを私のこころに重ね合わせる。ふたたび粘土を握りしめる。
30
まんべんなく拡がる階調の幅は、時として凡庸さをまぬがれないことがある。極端に、暗部の狭い幅で表現することもいいし、その逆の帯域での表現もある。しかし、それが成り立つには、諧調以外の要素が満たされたうえでの話である。
31
雲を撮って、これは<わたし>だ、といった男がいる。アルフレッド・スティーグリッツ。その表題は「equivalent」、同等のものとでも訳すのか。さて、私にとっての equivalentとは何だろうか。自己同一化の対象の発見こそが肝要である。
32
ジョルジュ・ブラックは自著のなかで、「芸術では、真理の歪曲なくして効果なし」と言っているが、この「真理の歪曲」を様々に言い換えると、美術史を楽しく旅することができるだろう。
美術史にかぎらず歴史を解きほぐすことは、創造的いとなみである。
33
暗室は垂直をめざす思考と、左右にゆれる運動の交点に立つ。
34
ふたたび、暗室ですること。
○色値の秩序と、その崩壊を見据えること
○フィルム面における「事件」の痕跡(ノイズの発生)と向き合うこと
○徐々に消滅していく形態(フォルム)の明証性と向かい合うこと
○存在と非在の境界を決する<しきい値>を読み切ること
何が写されていようが、結果としての「世界」の出現こそが、求めるモノの大前提である。
35
画像の変容過程を、リアルタイムで音像化することを考案している。動態的チャンス・オペレイション。
この計画をジョン・ケージと瀧口修造にささげたい。
田中孝道